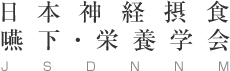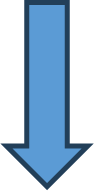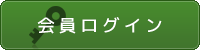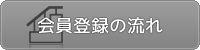高齢者への食支援(2025/01)
2025年の年明けとともに、いよいよ目の当たりとなった「2025年問題」と呼ばれる高齢化問題がテレビニュースでも取り上げられています。団塊の世代が後期高齢者になり生産年齢人口がさらに減少し高齢化率が30%を超えるため、社会的支援と高齢者の健康寿命をいかに保障するかが大切な鍵になると考えられます。
そこで今回は、高齢者への食の支援について、実例を交えてお伝えしたいと思います。
食べられる量が減ってきた、あるいは食べにくい様子がある場合、理由は複数考えられますが、食べやすくする工夫は大切です。さらに、下記に挙げるような支援も考慮して、誤嚥性肺炎の罹患を避けるよう努めましょう。
◆わかりやすくする工夫 |
 |
 |
|
 |
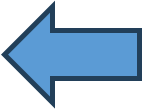 |
このような器もよく見かけます が外側の柄と器内の食物の区別 がつきにくく、食べ残しの原因 になってしまいます |
白内障、緑内障、黄斑変性症など高齢者が発症しやすい眼科的な症状や認知機能低下を伴うと、このような見分けにくい器では食べ残してしまうことになりかねません。
実際に私自身が勤める特別養護老人ホームで、介護士さんが器を変えたら白いご飯が食べられるようになった例があります。

見えにくい! 白い器に白いご飯 |
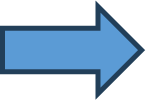 |

色のコントラストをはっきりさせるとわかりやすくなります |
||||||||||
 |
||||||||||||
| ◆高さの工夫 また、器からすくいやすくする、取りやすくするために、器やお膳に高さを調節することも大切です。腕、肩、体幹、腰をしなやかに動かすことが難しく、姿勢が崩れやすい高齢者の食事場面では、このような工夫をすることで、食事が楽にとれるようになります。食べにくくて時間がかかると疲労が増し、食べたくなくなってしまうこともあります。できるだけ自分の力で食事をとりやすくする工夫も大切です。 |
|
|||||||||||
|
|
 |
|||||||||||
| テーブルの上に台を置いて
お膳を乗せます |
 |
すくいやすくなりました |
2.口からのどのケア
下記のような問題が起こると、食べ物をよく噛んで飲み込みやすい形にすること(食塊形成)が難しくなり、飲み込みにくくなります。また、これらの問題によって時間がかかるようになり、疲れて食が進まなくなることもあります。できる範囲のケアを進めましょう。
①歯がかける、抜ける、義歯が合わない
⇒義歯を含めかみ合わせが悪いと、食塊形成がしにくいだけではなく、液体や柔らかいものを飲み込むときにもタイミングが合わなくなり、飲み込みにくくなります。むせやすい原因にもなります。歯科の診療を早めに受けましょう。訪問歯科を利用する方法もあります。
②唾液が出にくくなる:唾液は食塊形成に無くてはならないものです。加齢により唾液腺が萎縮して唾液の分泌量が減ったり、薬剤の影響で分泌量が低下することがあります。
⇒食前に唾液腺マッサージや口を動かす嚥下体操などを行うと良いでしょう。お薬の影響については医師、薬剤師に相談しましょう。
③唇や舌、のどの筋力が衰える:筋力は使わないことでも衰えます。食べられる方はよく噛んで食べることで機能維持につなげることができます。会話や歌うことも呼吸筋や口の筋肉を使います。じっと黙っていないで、お話をする機会を作りましょう。食事前の嚥下体操やカラオケも楽しみましょう。
④口腔衛生不良:上記②③の理由から、口の中に食べかすや痰などが残りやすくなります。食後の歯磨き、口腔清掃を心掛け、お口をきれいにしましょう。高齢者の肺炎は約8割が誤嚥性肺炎で、その多くが夜間の誤嚥によって引き起こされているとの報告があります1)。毎食後の口腔ケアが難しくても、特に就寝前にはきれいにすることを習慣づけましょう。
3.十分な栄養
元気を失う悪循環の源が栄養不良ということは、どなたも想像に難くないと思います。食べられる量が減ってくると、栄養状態も心配です。低アルブミ ン血症や低蛋白血症,body mass index(BMI)の 低下,貧血など栄養状態が低下すると肺炎にかかりやすくなることや、低栄養を改善すると血清アルブミン値や血清総蛋白値が上昇し、肺炎の予防効果につながったとの報告があります2)。
元気なうちから栄養バランスと栄養量を意識しながら食事をとることは大切ですが、少し怪しくなった時に周囲の方が注意を向け、望ましい栄養摂取方法をサポートできると助かります。定期的な栄養状態のチェックに加え、食事で摂れる栄養量の確認や、不足する際に可能であれば栄養補助食品を上手に用いることも一方法です。
4.食道、消化管の変化への対応
高齢者に多く起こる食道、消化管の症状への注意を向けておくことも大切です。胃腸の消化吸収力の低下に加え、円背や心肥大などにより食道が圧迫されることによる食道の通過障害、高度の円背では胃が圧迫されて一度に食べられる量が減ってしまうこともあります。また、胃食道逆流による胸やけ、食欲の低下、肺炎等に至らせないようにすることも大切です。「苦い味がする」という訴えがあったり、夜間就寝中に咳が出る場合は受診して診断、対応を受けるとよいでしょう。まずは、食後直ぐに横にならない習慣付けも大切です。
以上、今回は、高齢者の食支援についてお伝えしました。本人からの訴えに傾聴した対応が大切なことはもちろんですが、訴えを起こせない方に対してはケアを担当する方々の注意・観察力で支えられるよう努めて行きましょう。
参考文献
1)Teramoto S. Fukuchi Y, Sasaki H et al: High incidence of aspiration pneumonia in community and hospital acquired pneumonia in hospitalized patients: a multicenter, prospective study in Japan. JAGA56: 577-579,2008
2)山谷睦雄:誤嚥性肺炎の予防における口腔ケアおよび歯科診療の重要性.老年歯学.34-3.2019. P361-4
*写真は、許可を得て撮影しています。
埼玉県総合リハビリテーションセンター 言語聴覚科 / 埼玉医大福祉会
カルガモの家 特別養護老人ホーム あすなろの郷浦和
清水充子