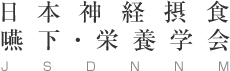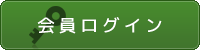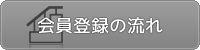災害時の食と服薬(2025/04)
大規模災害リハビリテーション対応マニュアル(日本リハビリテーション医学会)によれば、災害のフェーズ分類は 第1期「被災混乱期」第2期「応急修復期」 第3期「復旧期」第4期「復興期」である。このうち被災混乱期では 救命・救助が何よりも優先であり、まずは安全な場所へ避難することが必要であるが、その日から食生活が始まる。応急修復期になると救護・応急対応が始まり、避難所生活・食生活への支援が広がっていく。
日本神経摂食嚥下・栄養学会(JSDNNM)では、東日本大震災発生時には、被災地支援を経験した医療関係者の情報を収集し、主に食の支援についてJSDNNMコラム欄に数回にわたり掲載した。その後も多くの自然災害が発生したが、支援の具体的な状況や課題を調査したので、その内容の一部を報告する。
被災混乱期や応急復旧期では、被支援者への個別対応が難しい可能性もあり、摂食嚥下障害のある当事者も、平素より自ら避難生活に備えることが重要である。食のみならず、服薬への備えも必要であり、その備えをサポートするのもわれわれ医療職の責務と考える。
1)避難生活での注意点と対策
食形態:支援の食事を平素の嚥下調整食に近い状態に加工するため、携帯できる食品加工グッズを持参する。最近は粥も発災直後より提供されるようになったが、摂食嚥下障害に適した調理法など個別対応も必要であることを、共通理解することが必要である。
内服薬: 災害発生時には”移動薬局”としての機能を備えたモバイルファーマシーなど(災害対応医薬品供給車両)の導入が各地で進んでいる。発災初期より活動し、平素の内服薬と同効に近い薬剤が提供されるようになりつつあるが、服薬困難のある場合、剤形(粉砕・水薬など)への個別対応が難しい可能性もある。お湯が使える場合に限られるが、簡易懸濁法などを平素より導入しておくと役立つ。
口腔ケア:長く仰向けに寝ていると、噛む機能と口の衛生は悪化し肺炎の原因となるので、できるだけ座る時間を作る。水なしでもウエットティッシュなどで歯磨きをおこなう。また、義歯を長くはずしていると噛む力は低下するので、義歯はなるべくつける。
2)災害への備え
今後予測される災害に備えて、医療的・介護的ケアのあり方が自治体などで検討されつつあるが、被災混乱期・応急修復期には個別対応が難しい。摂食嚥下障害のある被支援者自身の備えとしては、以下のようなものが勧められている。
レトルトやフリーズドライのお粥・介護食などは、平素も食べながら備蓄するローリングストックを実施する。常用薬、とろみ剤、飲料水、クラッシュゼリー、経腸栄養剤などは消費期限が比較的短いことに注意する。さらに、食品加工の器具、口腔ケアセット、義歯のケアセット、マスク、使いなれた食器やスプーン、ストロー、ディスポの食器やジッパーつきビニール袋などを、防災グッズとして各自必要に応じて準備しておくとよい。
関西労災病院 脳神経内科 野﨑園子