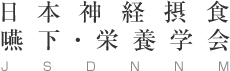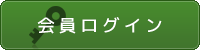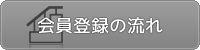第二回学術集会 さいたま大会
| 期 日: | 2006年8月26日(土) |
|---|---|
| 会 場: | 大宮ソニックシティ 〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 TEL 048-647-4558 |
| 会 長: | 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 川井 充 |
| 13:30~14:15 | 座長 川井 充 独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 特別講演 摂食・嚥下リハビリテーションと口腔ケア 大塚義顕 国立病院機構 千葉東病院歯科 |
|---|---|
| 14:15~14:30 | 休憩 |
| 座長 湯浅龍彦 国立精神・神経センター国府台病院 | |
| 14:30演題抄録を見る | 筋萎縮性側索硬化症患者に対する経口摂取再獲得への試み ―喉頭全摘術後のリハビリテーション― 草場 徹 国立精神・神経センター国府台病院 |
| 14:50演題抄録を見る | ALS嚥下・栄養管理マニュアルについて 市原典子 高松東病院 |
| 15:10演題抄録を見る | MSAの摂食嚥下障害アンケート報告 金藤大三 鳥取医療センター神経内科 |
| 15:30演題抄録を見る | 国立病院機構の神経内科病棟におけるPEG造設と管理の現状 野崎園子 国立病院機構徳島病院 神経内科 |
| 15:50~16:00 | 休 憩 |
| 座長独立行政法人国立病院機構徳島病院 | |
| 16:00 | 退院後も介護施設を利用しながらIOCが継続できている4症例 寺尾聡子 独立行政法人国立病院機構徳島病院看護部 |
| 16:20演題抄録を見る | 随意嚥下運動時の脳機能解析:fNIRSを用いた検討 山脇正永 東京医科歯科大学臨床教育研修センター・神経内科 |
| 16:40演題抄録を見る | 神経筋疾患患者における椎体前方突出による嚥下障害の検討 山本敏之 国立精神・神経センター武蔵病院 神経内科 |
| 17:00演題抄録を見る | 同一家族内での筋強直性ジストロフィー患者の嚥下造影の検討 大塚友吉 国立病院機構東埼玉病院リハビリテーション科 |
筋萎縮性側索硬化症患者に対する経口摂取再獲得への試み
―喉頭全摘術後のリハビリテーション―
国立精神・神経センター国府台病院
草場 徹
国立精神・神経センター国府台病院
志摩耕平,寄本恵輔,岩村晃秀,湯浅龍彦
【はじめに】
喉頭全摘術を施行した筋萎縮性側索硬化症患者に対し,経口摂取再獲得を目的としたリハビリテーションの介入効果について検討した.
【対象】
対象は胃瘻による栄養管理と侵襲的人工呼吸器による呼吸管理がなされている筋萎縮性側索硬化症患者3例.
【方法】
方法は各症例において具体的なリハビリテーションの取り組みについて報告し,喉頭全摘術前後における血液検査,胸部CT,経口摂取評価,簡易口腔・顎顔面機能評価,流涎量評価,QOL評価を比較した.
【結果】
結果,症例報告では経口摂取訓練プログラムに加え,継続的な離床や家族の協力により経口摂取が実施されていた.術前と比較し術後は,血液検査より栄養所見や炎症所見は維持・改善したが高脂血症が指摘された.胸部CTより肺炎所見は改善・消失,経口摂取評価や簡易口腔・顎顔面機能評価では全ての項目において改善が認められた.流涎量評価では口腔内吸引回数は不変であったが気管内吸引は減少した.QOL評価では高い満足度を示す一方で満足度が低下した症例も認めた.
【考察】
喉頭全摘術により誤嚥が完全に予防された中で行う積極的なリハビリテーションは,重度の嚥下障害があっても咀嚼や嚥下の機能を改善させるために必要不可欠な取り組みとなり,継続的な離床や家族の支援が経口摂取再獲得には重要であると考えられた.また術後より経口摂取量を見極めながらリスクを管理することに加え,患者や家族に適切な教育を実施していくことがQOL向上に寄与するものと考えられた.
ALS嚥下・栄養管理マニュアルについて
高松東病院
市原典子
*1徳島病院,*2松江病院(現:安来市民病院),*3医王病院,*4鳥取医療センター,*5山形病院,*6西別府病院,*7岩手病院,*8東埼玉病院,*9長崎神経医療センター,*10熊本再春荘病院,*11下志津病院,*12東名古屋病院,*13広島西医療センター
藤井正吾,野崎園子*1,石田 玄*2,沖野惣一*3,金籐大三*4,亀谷 剛*5,後藤勝政*6,鈴木靖士*7,布施 滋*8,松尾秀徳*9,箕田修治*10,本吉慶史*11,山岡朗子*12,渡邉千種*13
神経難病の嚥下障害については,近年まで疾患による障害の特徴が明らかでなかったこともあり,治療マニュアルは存在しなかった.そこで我々は,精神・神経疾患研究委託費「政策医療ネットワークを基盤にした神経疾患の総合的研究」研究班嚥下小グループの平成17年度の研究において,過去のエビデンスと研究班での研究成果をもとにALS嚥下・栄養管理マニュアルおよびアルゴリズムを作成した.
マニュアルは,外科的処置や人工呼吸管理を希望されるALS患者を基準に作成され,各嚥下障害の段階については,functional rating scale swallowing part(FRSsw)を使用した.
FRSsw4段階でのポイントは,病初期から嚥下障害,栄養状態,呼吸状態のモニタリングをおこない,嚥下・栄養障害が軽度な時期から,代償嚥下を考慮した摂食指導,嚥下食指導などの介入をおこなうことである.
FRSsw1~3段階では,各段階に応じた指導を進めるとともに,経管栄養方法の選択と導入時期の決定がポイントとなる.PEG造設の時期に関しては,呼吸機能とのからみが重要である.また,間欠的経管栄養法も症例を選べば非常に有用な方法である.有効な訓練方法の確立に関しては,今後の検討を要する.
FRSsw0段階でのポイントは,適切な栄養管理と,外科的治療法の選択および時期の決定である.ALS栄養管理基準の確立や,各種の誤嚥防止術の有効性に関しては今後の検討を要する.
MSAの摂食嚥下障害アンケート報告
鳥取医療センター神経内科
金藤大三
【目的】多系統萎縮症(MSA)患者ではしばしば嚥下障害が認められ中には誤嚥性肺炎や窒息を引き起こす例もある。しかしその病態、対策については十分のデータがあるとは言い難い。今回我々はMSAにおける摂食嚥下障害の現状を明らかにし、その対策を検討するためにアンケート調査を行った。
【方法】調査方法は国立病院機構に属する施設へのアンケート調査とした。調査は各施設2例程度任意に対称を選んだ。検討項目は⑥脊髄小脳変性症重症度分類⑦Yahr分類⑧認知障害有無⑨摂食嚥下障害重症度分類⑩合併疾患⑪薬剤⑫食事摂取の状態⑬食事の摂取状況⑭随伴症状・合併症など16項目とした。
【結果】1)症例の構成:22施設、51症例。平均年齢65歳2)認知障害の合併:認知障害合併65%。認知障害合併者は非合併者に較べSCD重症度の平均は高かった。SCD重症度が重症になるほど認知障害合併者の摂食嚥下障害重症度が非合併者に比べ重症化した。認知障害合併者はSCD重症度が同一でも経管栄養になる割合が高かった。認知障害合併者はSCD重症度が同一でも介助度が高かった。認知障害合併者の食べ方は「口からこぼれる」「こぼしながら食べる」「口に溜めたまま止まる」などの異常を示した。認知障害合併者はSCD重症度が同一でも流涎、湿声、咳・痰が多かった。3)パーキンソン症状の合併:SCD重症度が同一ならパーキンソン症状合併の有無で嚥下障害重症度に差はなかった。パーキンソン症状合併者は「前屈みで食べる」「水分で流し込む」などの食べ方の異常を示す傾向にあった。
【結論】:1.認知障害の合併は摂食嚥下障害を重症化し介助度を高め、さらに窒息や誤嚥の危険性を高める可能性がある。2.SCD重症度が同一ならパーキンソン症状合併の有無で嚥下障害重症度に差はなかった。
国立病院機構の神経内科病棟におけるPEG造設と管理の現状
国立病院機構徳島病院 神経内科
野﨑園子
2)国立病院機構奈良医療センター 神経内科(現:安東内科) 3)国立病院機構宇多野病院 神経内科 4)国立病院機構東名古屋病院 神経内科 5)国立病院機構兵庫中央病院 神経内科 6)国立病院機構刀根山病院 神経内科 7)国立精神神経センター国府台病院 神経内科
安東範明2) 小牟禮修3) 齋藤由扶子4) 舟川 格5) 松村 剛6) 湯浅龍彦7)
緒言:本研究は、国立病院機構の神経内科病棟におけるPEG造設の安全性と管理体制の現状と問題点を明らかにすることを目的とした。
方法:33国立病院機構の神経内科病棟担当医師に2005年12月現在の神経内科病棟のPEG造設と管理の現状について以下の項目について調査を行なった。
1)PEG造設の施行医 2)主治医と施行医の術前検討会 3)合併症を相談できる他科医 4)術前の患者への説明者 5)PEGクリニカルパス 6)PEG造設施設
PEG造設の施行医は、1)消化器外科医 21施設 2)消化器内科医 11施設 3)内視鏡医4施設 4)神経内科医 3施設 5)消化器以外の外科医、又は内科医 4施設 6)その他1施設で(複数回答可)、消化器外科医が多かった。神経内科の主治医と施行医の術前検討会は13施設でしかおこなわれていなかった。PEGのクリニカルパスは21施設で使用されていた。
PEGの各合併症について相談する医師については、呼吸不全については自分で対応するが24施設で最も多く、手技上のトラブルでは消化器外科医が22施設と最も多かった。自己抜去、感染、消化器症状、腹壁のトラブルについては、約半数の施設が消化器外科医に相談していた。相談できる消化器専門医のいる施設は約半数であることが伺われた。
他科医のPEGの合併症への対処については、8施設が不満と答えた。
合併症の解決した割合は、ほぼ全例が16施設、8割程度が14施設、6割程度が3施設、5割以下が1施設であった。患者・家族に対するPEGの説明は、主治医が33施設に対して、外科医は18施設と約半数であった(複数回答)。
PEGを他施設へ依頼する場合、入院によるものが8施設、外来によるものが4施設あり、7施設がPEGの専門医がいないために困っていることがあると答えた。また、院内でも6施設で、PEG施行を医師に断られたことがあるとの回答があった。
結語: PEG造設と管理について、他院での造設も含め、他科医との連携の難しさが伺われた。
退院後も介護施設を利用しながらIOCが継続できている4症例
独立行政法人国立病院機構徳島病院 看護部
寺尾 聡子
独立行政法人国立病院機構徳島病院 看護部 1)~4) 同 臨床研究部 5)
高居 智美1),宇田 裕岐2),野田 美幸3),佐藤 陽子4), 野崎 園子5)
【目的】当院は神経筋難病の機関病院であり、経管栄養法の選択肢の一つとしてIOC(間欠的経口経管栄養法)を選択している。入院中にIOCが習得されても退院となると、やむを得ず胃瘻を増設する患者も多い。これは、介護施設側にIOCが周知されていないことや経鼻法に比べるとやや手技が煩雑なことが影響しているのではないかと考える。
しかし、このような中、4例の患者が在宅で介護施設でもIOCを続けている。この継続の秘訣はどこにあるのか、また、今後も地域の介護施設と良い関係が築け、IOCの患者が受け入れられるにはどのようにすべきなのか考察した。
【対象と方法】1.退院後IOCを継続している患者が利用している介護施設の職員(3施設9名)に独自に作成したアンケートを施行。2.対象患者4名のIOC初期の様子をカルテから収集 上記1.2から何が効果的だったかを考察した。
【結果と考察】1.マンパワーの大切さ。今回は4例ともデイサービスの短期利用であるが、マンパワーの確保は重要である。介護施設でIOCの患者が受入れられた理由として、「ナースが勤務している時間帯だった」「スタッフが揃っていたこと」「経験あるナースが何人かいた」という意見のように看護師の存在に寄る所が大きかった。2.受け入れ先の理解と協力。利用者のIOCを見るまでIOCのことを知らなかったという者が多く実際に見るまでは不安もあり施設での初回IOC時はお互い緊張したようである。しかし、利用者のために、と快く協力してくれている姿が目に浮かぶ。今後も患者を通してお互いに情報交換をしてゆきたい。
3.入院中の教育。IOCのイメージをとらえやすいようにビデオ指導を行っている。また、スムーズな理解・手技の獲得に向けてIOCのクリティカルパス(試行段階)や技術チェックリストを用いている。中でも同じIOCを行っている患者(家族)同士での情報交換が理解促進に効果的である。
4.チーム医療の大切さ。在宅療養に理解のある医師が、「その人のためにIOCは必要」という姿勢で在宅にむけ協力を求め、結果的に良い流れが生まれている。今後もチームでIOCの啓蒙を広めてゆきたい。
随意嚥下運動時の脳機能解析:fNIRSを用いた検討
東京医科歯科大学臨床教育研修センター・神経内科
山脇正永
1同老人看護学 2同高齢者歯科学 3同リハビリテーション部
千葉由美1、戸原 玄2、植松 宏2、森田定雄3、水澤英洋
(対象・方法)
右手利きの健常男性16名(年齢20~42)を対象とした。プローブは帽子型の固定装置を用い、顔面から口腔咽頭に関連する運動感覚野について計測を行った。被検者は座位を保ち、頭位・姿勢は平素の摂食嚥下動作と同様にして行った。タスクとしては咀嚼、口輪筋収縮、咽頭筋収縮、口腔咽頭刺激、舌運動、自然嚥下運動、随意嚥下運動について解析した。
(結果)
嚥下運動のphaseによってNIRS信号分布が経時的に一定のパターンを示した。随意嚥下運動時には反射嚥下運動時に比べてoxyHb、deoxyHbの変動が有意であった。随意嚥下運動及び反射嚥下運動時におけるNIRS信号分布に有意な左右差は認めなかった。
(考察)
嚥下時の脳機能活動部位については、外側中心前回、補足運動野(SMA)、前帯状回、島及び前頭弁蓋、中心後回と頭頂葉、側島葉の報告がある。本研究では主として外側中心前回付近について解析を行ったが、随意嚥下運動においては自然嚥下運動に比してNIRS信号強度の変化が大きく、同部位の関与が示唆された。努力性の嚥下運動は自然嚥下運動とは異なるメカニズムである可能性があり、その解明は神経筋疾患の嚥下障害治療・リハビリテーション戦略上重要と考えた。>
神経筋疾患患者における椎体前方突出による嚥下異常の検討
国立精神・神経センター武蔵病院 神経内科・リハビリテーション科
山本敏之
(1) 国立精神・神経センター武蔵病院 神経内科, (2) 同 リハビリテーション科 (3) 同 整形外科
岸育世(2),清水加奈子(2),永江順子(2),濱田康平(2),竹光正和(3),小林庸子(2),村田美穂(1)
【目的】嚥下機能障害が起こりうる神経筋疾患において,骨棘や前縦靱帯骨化による椎体の前方突出が嚥下動態にどのような影響を与えるか,嚥下造影検査(VF)から検討した.
【対象と方法】パーキンソン病(PD)患者 78人,筋強直性ジストロフィー(MYD)患者 49人,筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者 19人を対象とした.VF前のレントゲン写真で第3頸椎から第1胸椎までの椎体前方突出部位を評価した.VFでは,被検者が坐位で液体バリウム10mlを嚥下し,検者が側面から30フレーム/秒でビデオに記録した.椎体の前方突出による残留を「通過異常あり」として評価した.
【結果】頸椎の前方突出を認めたのは,PD患者 10人(12.8%),MYD患者 6人(12.2%),ALS患者 6人(31.6%)であった.第3頸椎と第4頸椎に前方突出を認めた患者はいなかった.第5頸椎と第6頸椎間の突出は4人に認め,ALS患者1人とMYD患者2人では下咽頭での通過異常があり,PD患者1人では通過異常はなかった.第6頸椎から第7頸椎間の突出は10人に認め,PD患者 1人では下咽頭から食道にかけての通過異常があり,MYD患者 2人では下咽頭での通過異常があり,PD患者 4人とALS患者 3人では通過異常はなかった.第7頸椎から第1胸髄間の突出は3人に認め,MYD患者 1人が食道での通過異常があり,PD患者 2人では通過異常はなかった.連続した3椎体の前方突出は,ALS患者 2人,MYD患者 1人,PD患者 2人に認め,いずれも下咽頭から食道にかけての通過異常があった.
【考察】一般に椎体の前方突出は嚥下動態に影響を与えるとされている.嚥下障害が起こりうる神経筋疾患患者に椎体の前方突出が合併した場合,連続した3椎体の椎体の前方突出では液体の通過異常をきたしやすいことを示した.また,MYD患者に椎体の前方突出を合併した場合,いずれの椎体部位であっても,ALS患者やPD患者に比べて,通過異常が出現しやすい可能性があることが示唆された.原疾患による嚥下障害の程度や椎体の前方突出の程度によって嚥下への影響は異なると予測でき,より多数例において検討する必要があると考えた.
同一家族内での筋強直性ジストロフィー患者の嚥下造影の検討
独立行政法人国立病院機構東埼玉病院
大塚友吉
市川市リハビリテーション病院
*和田勇治
【はじめに】筋強直性ジストロフィー(MyD)患者において嚥下障害はよく認められる症状の一つであるが、家族例での検討は少ない。今回我々は同一家族内での先天型・小児発症型・古典型のMyD患者の嚥下造影検査(VF)を行い、比較検討した。
【症例1】11歳男性。在胎28週で帝王切開にて出生。誤嚥性肺炎の既往あり。CTGリピート数1260。斧状顔貌・高口蓋あり。頚定・四肢自発運動・発語なし。離乳食後期相当の食事を介助で摂取。VFでは、口腔期の食塊移送と咽頭期の喉頭挙上がやや不良。
【症例2】21歳男性。症例1の兄。10歳頃より把握性筋強直や低運動能力で発症。CTGリピート数730。前頭部脱毛・高口蓋・斧状顔貌・把握性筋強直・叩打性筋強直・四肢遠位部の筋力低下あり。常食摂取。VFでは、咽頭収縮や喉頭挙上が不良で、食塊の喉頭蓋谷残留・梨状陥凹残留あり。
【症例3】49歳女性。症例1・2の母。6年程前から把握性筋強直が出現し、その後階段昇降が困難となった。CTGリピート数530。前頭部脱毛・高口蓋・把握性筋強直・叩打性筋強直・軽度四肢筋力低下あり。常食摂取。VFでは、喉頭蓋谷に食塊の軽度残留を認めたが、水分で除去可能。
【考察】一般的にMyDでは、CTGリピート数と臨床症状が比例し、世代を経るたびにCTGリピート数が増大する表現促進現象が認められるとされ、嚥下機能について同一家族内でその傾向が確認された。同一家族内同一疾患であっても発症時期により嚥下状態が異なり、個別の嚥下機能評価や摂食指導が重要と考えられる。